「原価の把握と活用講座」開催のご案内
中小企業は、構造的な人手不足、最低賃金引上げ等の賃上げ問題のほか、米国関税問題といった新たな課題に直面しており、自社の企業努力では吸収しきれないコスト高騰分を適正に価格に転嫁していく必要に迫られています。
価格交渉では、定期的な取引価格の見直しや原価上昇の状況の共有などが重要とされており、そのためには、自社の製品の原価の現状把握が必要です。
そこで、本講座では、原価管理の基礎知識(原価計算の基本や賃金上昇が経営に与える影響、現場の改善活動がもたらす効果など)を学んでいただき、コスト高騰分を適正に価格に転嫁し、価格交渉の事前準備までのイメージをつかんでいただきます。
令和7年度ものづくり工場管理実践塾上級編セミナー「原価の把握と活用講座」
~自社の原価を把握・改善し、適正な価格設定・価格転嫁の推進を目指して~
対象者
島根県内ものづくり企業の経営者・製造現場のリーダークラス・中堅社員・財務担当者等
開催概要
日時
【基礎編】 令和7年10月28日㈫ 10時~17時 (休憩・質疑応答含む)
【活用編】 令和7年11月18日㈫ 10時~17時(休憩・質疑応答含む)
会場
いずも企業交流館(NPO法人ミライビジネスいずも)/出雲市斐川町神氷2535-10
受講方法
会場受講となります。(オンライン受講形式はございません。)
基礎編・活用編の両方の受講をお勧めしますが、いずれかを受講いただいてもかまいません。
※各回受講数は2名までとさせていただきます。
定員
30名
受講料
無料
申込締切
令和7年10月21日(火)
※ 定員に達した場合は、早めに応募を締め切ることがございます。
カリキュラム
基礎編:原価の把握、賃金上昇の影響、現場改善の経営効果の把握
Ⅰ. 原価計算の目的と原価の構成要素
1.モノの作り方と原価
2.原価計算の役割と方法
Ⅱ 損益分岐点と限界利益・CVP分析の基礎
Ⅲ 累積限界利益管理
Ⅳ 人件費・賃金上昇による財務への影響等について
(労務費の上昇に対する対応策の立案)
Ⅴ.不良率改善・生産リードタイム短縮(=現場の2S/5S改善)の経営効果
1.手余り応対と手不足状態の不良率改善
2.生産リードタイム短縮の経営効果
活用編:原価の改善・課題解決、価格交渉の事前準備
Ⅰ 原価改善活動の体系的な進め方
1.職場で取り組む原価改善
2.更に原価改善を進める方策
(1)原価改善のコツ(具体的な取り組みのポイント)
(2)自社の原価改善活動をさらに進化させる方法を考える
Ⅱ CVP分析を活用した利益管理
経営環境の変化(資源価格高騰・労務費上昇)に対応する利益計画の立案と対策の実施
1.製造業の損益分岐点の特徴
2.経営環境の変化と工場の損益分岐点の変動(コスト高騰と労務費上昇)による変化
3.経営環境の変化(資材価格高騰・労務費上昇)を織り込んだ工場利益計画の作成
Ⅲ 価格交渉の事前準備
限界利益分析と価格交渉のポイント・進め方
Ⅳ 付加価値を生み出す具体的方策の実践
1.限界利益を増やす営業活動
2.限界利益を増やす開発活動
3.限界利益を増やす製造活動
※本講座は、令和6年度の「原価講座」基本編・実践編・応用編のカリキュラムの構成を、昨今の経営課題をふまえて変更したものです。
案内チラシ
![]() 「ご案内(チラシ)」をダウンロードする(PDF:1.3MB)
「ご案内(チラシ)」をダウンロードする(PDF:1.3MB)
講師紹介
足立 直樹 氏

・あこう管理会計コンサルティングLLP代表
・名古屋工業大学客員教授
〈 略歴 〉
トヨタグループで事業部門・コーポレート部門の部門長を歴任、2018年、名古屋大学大学院博士後期課程産業経営システム専攻修了(博士号取得)。
国内外の事業企画・経営企画・経理部門の実務経験と産業経営システムを中心とした最新の学術研究をベースとして、大学・大学院での管理会計教育およびコンサルティング、分かり易いセミナー事業を推進し、受講者が真に役立つ知識の修得ができたと思える教育を心掛けています。
申込方法
申込フォーム、または下記の申込書に必要事項をご入力のうえ、e-mailにて申し込みください。
お問い合わせ先
公益財団法人しまね産業振興財団
経営支援課 金津・梅木
Tel:0852-60-5115/Fax:0852-60-5105
Mail:con@joho-shimane.or.jp
 支援ツールから探す
支援ツールから探す 目的から探す
目的から探す
 その他のサービス
その他のサービス

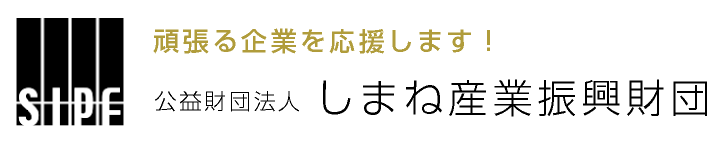

 支援ツールから探す
支援ツールから探す
 目的から探す
目的から探す
 その他のサービス
その他のサービス
 組織から探す
組織から探す
