「ゴム配合・成形加工のトラブル原因追求と解決の勘所」講座開催のご案内
~ゴム配合トラブルの原因と対策/ゴム成形のトラブル現象の原因と対策/ゴム製品の機能と物性の不適合/接着不良などのトラブルと対策~
ゴム製品の開発や製造においては、配合や成形加工の工程で思わぬトラブルが発生し、品質不良や機能不適合につながることがあります。本セミナーでは、ゴム配合におけるトラブルの原因と対策、成形加工における不良現象の要因と解決のヒント、さらに接着不良や物性の不適合など、現場で頻発する課題を具体的に解説します。長年の経験と事例をもとに、トラブルの「原因追求の勘所」と「効果的な解決策」をわかりやすく整理し、実務に直結する知見を提供します。
ゴム配合や成形技術に携わる担当者の方はもちろん、管理職や若手技術者の方々にも役立つ内容です。
講座内容
1.ゴム配合のトラブルとその原因と対策
1.1 オゾンクラック
1.2 ブルーム(ブルーミング)
1.3 ブリード
1.4 汚染
2.成形工程のトラブル現象とその原因と対策
2.1 形状不良(変形)
2.2 寸法不良
2.3 ゴム材質不良
2.4 外観不良
3.ゴム製品の機能とゴム物性との不適合
3.1 Oリングは丸ベルトではない
3.2 シリコーンゴムOリングの膨潤
3.3 ゴムの臭い
3.4 ウレタンゴムの加水分解
3.5 ゴムの固着
3.6 -40℃の耐寒性
3.7 クッションゴムの過荷重破壊
3.8 摩擦(friction)
4.その他のトラブルと対策
4.1 接着不良
4.2 硬度不良
4.3 員数不足
講師
大坪 一夫 先生 (ゴム技術コンサルタント)
[略歴]1941年東京都墨田区生まれ。1964年3月千葉工業大学工業化学科卒業。同年4月(株)東京ゴム製作所に入社。1980年9月岡山ゴム興業(株)(現株式会社岡山)に入社。2000年3月同社退社。現在ゴム成形技術に関する著書の執筆、ゴム技術コンサルタント、セミナー講師として活動。
[著書]「ゴム成形技術」、「ゴム材料技術」、「ゴム加工技術」、「ゴム金型活用ハンドブック」
対象者
・ゴム配合や成形加工において課題を感じている担当者
・ゴム製品の開発・製造に従事している技術者や管理職の方
・ゴム配合・成形技術を学び直したい方
・ゴム材料やゴム製品を取扱う企業の担当者
開催日時
令和7年11月18日(火)10:00~17:00(受付 9:30~)
会場
(1)メイン会場:テクノアークしまね 大会議室(松江市北陵町1)
(2)サテライト会場:いわみぷらっと 会議室(浜田市相生町1391-8 シティパルク浜田)
※メイン会場での講義をライブ中継し、サテライト会場にてご覧いただきます。
参加費
2,200円(税込)/人
※講座終了後、請求書を郵送いたします。
定員
(1)メイン会場:30名
(2)サテライト会場:20名
※いずれも県内企業優先
申込方法
申込みフォームまたは下記の申込書に必要事項をご記載のうえ、FAXまたはEメールにてお申し込みください。
※お申込みの際は、チラシ裏面もしくはお申込みフォームに記載の【注記】を必ずご確認ください。![]() 「チラシ」をダウンロードする(PDF:1.9MB)
「チラシ」をダウンロードする(PDF:1.9MB)![]() 「申込書」をダウンロードする(PDF:1.0MB)
「申込書」をダウンロードする(PDF:1.0MB)
【注意点】
・上記お申込みフォームにて4名以上お申込みの場合は、人数に合わせて複数回ご入力いただき送信してください。
・ご受講の可否については、申込締切(11/7)後の2営業日以内にメールにてご連絡をいたしますので、連絡者のメールアドレスは必ずご記入ください。
(※講座開催日の3日前までにご連絡が届かない場合には、お手数ですが下記のお問い合わせ先までご連絡ください。)
・受講決定後にキャンセルされる場合は、受講料を請求させていただき、講座で使用するテキスト類を送付いたします。予めご了承ください。
申込締切
令和7年11月7日(金)17:00
主催/協力機関
公益財団法人しまね産業振興財団/島根県産業技術センター
◇お問い合わせ◇
<申込み等に関すること>
公益財団法人しまね産業振興財団
創業・人材支援課(担当:布野・新宮)
電話:(0852)60-5117
FAX:(0852)60-5116
E-mail:ihrd@joho-shimane.or.jp
<講座の内容に関すること>
島根県産業技術センター
化学材料科(担当:金山)
TEL:0852-60-5140(代表)
 支援ツールから探す
支援ツールから探す 目的から探す
目的から探す
 その他のサービス
その他のサービス

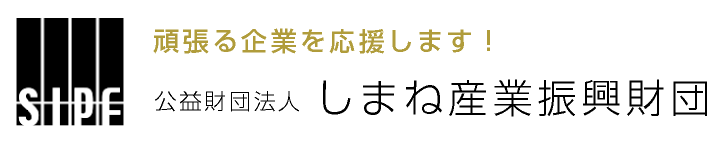

 支援ツールから探す
支援ツールから探す
 目的から探す
目的から探す
 その他のサービス
その他のサービス
 組織から探す
組織から探す
