「品質工学基礎講座~開発効率向上と品質問題防止を両立する手法~」開催のご案内 ※募集は終了しました
※募集は終了しました
品質工学(タグチメソッド)は製品の品質をものづくりの上流で確保し、市場や量産工程で発生する問題を未然に防止する手法です。
一般に上流(研究開発)での品質評価は精度が悪い上に、コストと工数(時間)が必要となりますが、品質工学では品質より機能を評価することで開発を効率化します。品質問題は機能のばらつきが原因で発生するため、機能の安定性を改善し向上させることが品質問題の未然防止につながります。
また、実際の製品は、使用条件のばらつき、使用部材のばらつき、劣化などの技術者の制御できない誤差因子(ノイズ)の影響を受けます。従来の一般的な開発手法では、ノイズの存在を考慮せず進めるため、最終段階になってノイズの影響による様々な品質問題が発生し、手戻りが発生します。品質工学は、ノイズの存在を前提にして開発を進め、ノイズがある状態で性能を満たすだけではなく、ノイズの影響を受けにくい製品の開発を行う手法、つまり開発の初期段階から品質を作りこみ、手戻りを激減させる手法です。
このセミナーでは品質工学の考え方と使い方を中心に、演習や成功事例の紹介などを交え、実践的かつ初めて学ばれる方にもわかりやすい内容となっております。
講座内容
| 1日目 | 品質工学の概要と機能性評価 |
| 1. 品質工学の成り立ちと全体像 1.1 品質工学とは 1.2 科学と技術の違い 1.3 品質工学の狙い 2. 機能性評価の考え方と進め方 2.1 基本機能を定義する 2.2 誤差因子の複合化 2.3 直交表について 2.4 ばらつきを定量化するSN比 3. 演習 ・SN比の計算 ・基本機能の定義 ・誤差因子抽出と複合化 4. 機能性評価によるサプライヤの技術力判定 5. ソフトウエアの機能性評価 6. まとめ、質疑応答 |
|
| 2日目 | パラメーター設計による機能改善 |
| 1. パラメータ設計の考え方と進め方 1.1 パラメータ設計の目的 1.2 パラメータ設計の手順 2. 演習 ・パラメータ設計の計画立案 ・模擬データによる最適条件の選定と解析 3. シミュレーション技術との融合 4. 成功事例の紹介 5. まとめ、質疑応答 |
|
※ 演習にはMicrosoft Excelとマクロを使用します。
(演習用テンプレートファイル(Excel形式)はお持ち帰りいただき、自社での取り組みにご利用いただけます。)
開催日時
令和5年9月21日(木)、22日(金)
両日とも 10:00~17:00(受付 9:30~)
会場
島根県産業技術センター 2階 プロジェクト研究室(松江市北陵町1番地 テクノアークしまね)
講師
芝野 広志 氏(TM実践塾 代表)
1980年大阪市立大学工学部電気工学科卒業。同年ミノルタカメラ(株)(現コニカミノルタホールディングス(株))に入社、OA機器に関連する製品設計、開発業務に従事。
2015年コニカミノルタ(株)退職。2016年TM実践塾代表。
【所属団体】品質工学会理事。関西品質工学研究会顧問。
【活動内容】日本規格協会講師(品質管理、品質工学)。京都府特別技術指導員(企業指導、セミナー講師)
品質工学会貢献賞、研究発表大会金賞、銀賞、優秀論文金賞を受賞。
対象者
・島根県内の製造業に従事しておられる開発・設計・品質保証・生産技術・製造部門の技術者の方
・品質工学(タグチメソッド)に興味をお持ちの方
習得知識
・品質問題を未然に防止するシステム評価の方法(機能性評価)
・品質改善とコスト削減を両立する設計手法(パラメータ設計)
携行品
・筆記用具
・ノートパソコン(Microsoft Excelとマクロが使用できること)
参加費
3,000円/人(税込)
※お支払方法は、講座終了後に申込連絡者様宛てにお知らせいたします。
定員
15名(先着順)
※受講条件:島根県内に事業所等を有する企業であること
申込方法
※募集は終了しました
こちらからお申込みください。
※お申込みの際は、上記申込みフォームに記載の【注記】を必ずご確認ください。![]() 「チラシ」をダウンロードする(PDF:666kB)
「チラシ」をダウンロードする(PDF:666kB)
【注意点】
・ご受講の可否については、申込締切(9/12)後の2営業日以内にご連絡をいたします。
(講座開催日の2日前までにご連絡が届かない場合には、お手数ですが下記のお問い合わせ先までご連絡ください。)
・受講決定後にキャンセルされる場合は、受講料を請求させていただき、講座で使用するテキスト類を送付いたします。予めご了承ください。
申込締切
令和5年9月12日(火)17:00
その他
・本講座は雇用調整助成金等の助成金の対象となる場合がございます。詳細は最寄りのハローワーク等にご確認ください。
・新型コロナウィルス感染症対策について、国や県の対応に順じて実施する予定です。なお、感染状況によっては講座の延期や中止になる場合がございます。予めご了承ください。
主催/協力機関
(公財)しまね産業振興財団/島根県産業技術センター
◇お問い合わせ◇
<申込み等に関すること>
(公財)しまね産業振興財団
創業・人材支援室(担当:布野・新宮)
電話:0852-60-5117
FAX:0852-60-5116
E-mail:ihrd@joho-shimane.or.jp
<講座の内容・携行品に関すること>
島根県産業技術センター
電子・電気技術科(担当:川島・大峠)
TEL:0852-60-5138(直通)
 支援ツールから探す
支援ツールから探す 目的から探す
目的から探す
 その他のサービス
その他のサービス

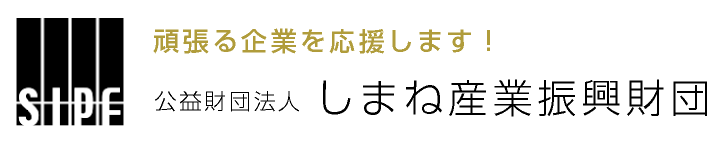

 支援ツールから探す
支援ツールから探す
 目的から探す
目的から探す
 その他のサービス
その他のサービス
 組織から探す
組織から探す
